- ▶津田貴司・福島恵一『音響・環境・即興 松籟夜話――〈耳〉の冒険』
- ▶『日めくりジャズ365 2026年版』
- ▶『超ジャズ 杉田誠一著作・写真集』
- ▶『日めくりジャズ365 2025年版』
- ▶岡島豊樹『古典邦楽十吋盤のすすめ』
- ▶稲岡邦彌『新版 ECMの真実』
- ▶岡島豊樹『地中海ジャズの歴史と音盤浴案内』
- ▶齊藤聡『齋藤徹の芸術 コントラバスが描く運動体』
- ▶津田貴司=編『フィールド・レコーディングの現場から』
- ▶中村隆之『魂の形式 コレット・マニー論』
- ▶岡島豊樹『東欧ジャズ・レコード旅のしおり』
- ▶岡島豊樹『ソ連メロディヤ・ジャズ盤の宇宙』>
- ▶細田成嗣=編『AA 五十年後のアルバート・アイラー』
- ▶自由爵士音盤取調掛『日本フリージャズ・レコード図説』
- ▶津田貴司=編『風の人、木立の人』
- ▶『ハリー・スミスは語る 音楽/映画/人類学/魔術』
- ▶ジョン・コルベット『フリー・インプロヴィゼーション聴取の手引き』
- ▶hikaru yamada hayato kurosawa duo 『we oscillate!』
- ▶大里俊晴『間章に捧げる即興演奏』
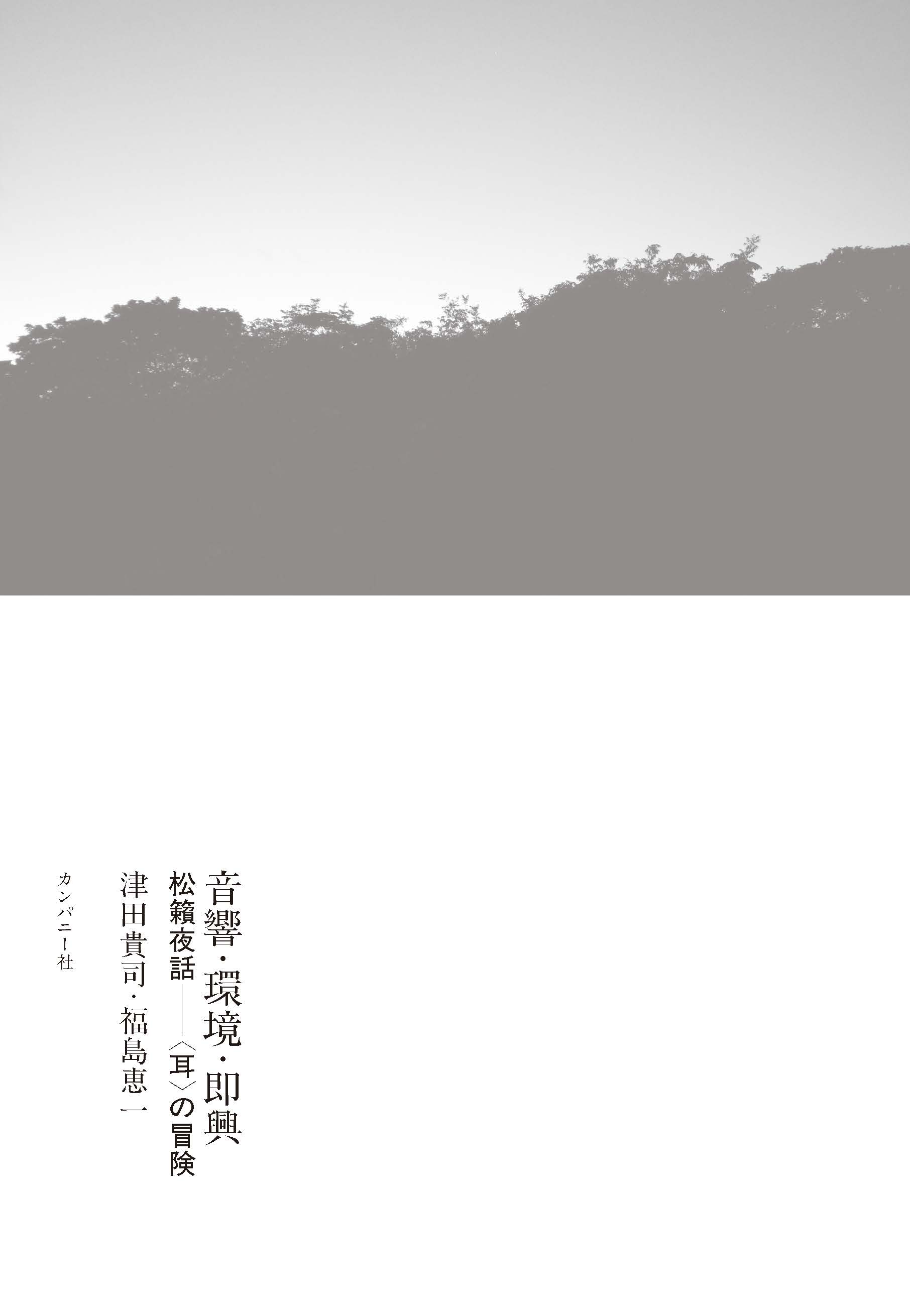
音響・環境・即興 松籟夜話――〈耳〉の冒険
著者 津田貴司・福島恵一
四六判並製:592頁
発行日:2025年12月
本体価格:3,800円(+税)
ISBN:978-4-910065-17-5
デザイン:川本要
▼目次
●はじめに
Ⅰ|松籟夜話への助走
●第1章 コンセプト、配置・布置
1. 主要コンセプト
2. 集まっていっしょに聴くこと
3. 言葉を交わす(差し挟む)こと
4. 録音を聴くということ
5. 松籟夜話の求める場のあり方
6. 音を聞き分け、結びつける耳の原理
7. 松籟夜話の志向を具体的に造形する歸山スピーカー
8. 発想・思考の補助線とそれを生み出すアーカイヴ
Ⅱ|松籟夜話の実践
●第一夜 ミシェル・ドネダと「予兆」
1. 環境とドネダ
2. ドネダと声
●第二夜 音響化する音を捉えるデイヴィッド・トゥープの野生の耳
1. 熱帯雨林という力の場
2. 即興演奏に噴出する過剰な力
3. 溶けていく輪郭、見出される新たなかたち
●第三夜 熱帯雨林を聴くフランシスコ・ロペスの耳の「視界」
1. 熱帯雨林への入り口
2. 熱帯雨林の深奥へ
3. 熱帯雨林に惑わされる
●第四夜 スティルライフによるスティルライフ
1. 身体が理解した(以前から知っている)音
2. 素材の質感
3. 場所性、場所を演奏する
4. 想像的風景
5. 混じりけなしのフィールド・レコーディング
6. 旅路を思い返しつつ現世へと浮上する
●第五夜 ジム・オルークを光源として、音と響きの間を照らし出す
1. ジム・オルークの耳を借りる
2. 沈黙/ざわめき/環境
3. 振動/マテリアルな現象
4. 溶解/変容/襞/気象/分泌/派生
5. 「無景映画」的推移/モンタージュ
●第六夜 360° records 特集・1――tamaruを中心に
1. 音をして語らしめる
2. 音の振る舞いを見つめる耳のまなざし
3. 音へと向かう身体の態勢
●第七夜 360° records 特集・2――Amephoneを中心に
1. 特定の色や匂いを持つ空間、記憶を持った場所
2. 「捏造」民族音楽
3. 映画的な空間構成
4. 空間による音の変容への眼差し
●第八夜 漂泊する耳の旅路=現地録音を聴く・1――聖なる場所に集う声
1. 複数の煙が立ち上るような声の集積が、その場所を照らし出していく
2. 複数の煙が立ち上るような声の集積が、声の身体を照らし出していく
3. 声の照らし出す空間、環境を触知する息
●第九夜 漂泊する耳の旅路=現地録音を聴く・2――音響都市の生成
1. スナップショットが浮かび上がらせる都市像
2. 俯瞰と転送――都市空間における身体の位相
3. 路傍の芸
4. 音響都市の生成
●第十夜 漂泊する耳の旅路=現地録音を聴く・3――移動する音、生成中の音楽
1. 移動/交通による生成と距離のもたらす断絶――あるいは甘さと苦さ
2. 隣接する異郷、変調される音響/変容するリアリティ
3. 幻想の大陸の彼方へ
Ⅲ|松籟夜話の核心
●第2章 耳の眼差し
1. 聴く体験と知ること
2. 注意と対象化
3. 能動的な行為としての「聴くこと」
4. 耳の視界=聴覚のフレーム
5. 距離と内感、音と振動
6. 空気という媒質の手触り
7. 音に伴う触感
8. 聴覚と視覚・1――聴くことに対する見ることの優位
9. 聴覚と視覚・2――視覚なしの聴取
10. 感覚の先端、知覚の手前
●第3章 オールオーヴァー
1. 『La Selva』の衝撃
2. オールオーヴァーとは
3. 音/響きのオールオーヴァー・1――再定義
4. 写真への迂回
5. 絵画(セザンヌ)への迂回
6. 音/響きのオールオーヴァー・2
7. 補論・1――サウンド・マターについて
8. 補論・2――アコースマティックについて
●第4章 暗騒音――いまそこにあるざわめき
1. 暗騒音とは
2. 暗騒音を聴く
3. 暗騒音と場所
4. 空間を満たしている響き=包囲音
5. 〈地〉の隆起と〈図〉の浸食
6. 「暗騒音」の能産性――ざわめきから生成するもの
7. 「暗騒音」から析出してくるもの
●第5章 地質学的想像力
1. 地質学的想像力とは
2. ヴァナキュラーな声と空間
3. 力の痕跡、形態の生成、「いま・ここ」で拮抗する力をまざまざと感じとること
4. 飛び火――空間的/時間的な「遠さ」を隔てて
5. 深淵へ
●第6章 ダイアグラム
1. ダイアグラムとは
2. 松籟夜話のダイアグラム・1――〈音響・環境・即興〉
3. 松籟夜話のダイアグラム・2――〈音響・環境・即興〉の動詞化
4. 松籟夜話のダイアグラム・3――二つの三角形
5. フランシスコ・ベーコンのダイアグラム(創造の契機として)
6. ジャン゠リュック・ゴダールのダイアグラム
7. プレート・テクトニクス
8. 松籟夜話のダイアグラム・4――三次元化による正八面体
9. 松籟夜話のダイアグラム・5――向かい合う二つの面/膜
10. 付論・1――〈音響・環境・即興〉のパラフレーズ
11. 付論・2――昼間賢の「即響」(「音響音楽論」より)
●第7章 〈興〉の詩学
1. 大伴家持における「興」――和歌の六義
2. 中国古典解釈における「興」――自然風景の呈示
3. 日本における「興」の展開――歴史的再検討
4. 日本上代・中古における〈興〉――原初の豊かさとその後の物象の力への不信
5. 生のイメージとテクスト・1――「外部」の喪失/テクストへの自閉
6. 生のイメージとテクスト・2――「外部」と「内部」の緊張関係
7. 基本的コードの継続
8. 『源氏物語』のサウンドスケープ
9. 言語の働きを成立させている基本的な二つの要素としての〈興〉〈観〉
10. 「引譬連類」の動作原理――イマージュと力(デュナミス)
●第8章 録音という汲み尽くせないもの――ドキュメンタリー映画との比較において
1. ドキュメンタリー映画という手がかり
2. ドキュメンタリー映画と録音(フレーミングとマイキング)
3. フィールド・レコーディングに映り込むもの
4. 即興演奏の録音は単なる記録か
5. 録音/聴取の「現場」とはなにか
6. 録音における「汲み尽くせないもの」
●第9章 聴取の能動性――フィールド・レコーディングとワークショップの体験に基づいて
1. 音の情動を聴き取る能力
2. フィールド・レコーディングから聴き取れるもの
3. フィールド・レコーディングの体験より
4. 音の消息を追う耳の眼差し
5. 喧騒と静寂、音の「図」と「地」
6. 「みみをすます」の実践
7. フィールド・レコーディングを聴き取るということ
●第10章 変容していく都市のイメージと文化人類学の状況
1. 文化の変容・混淆
2. 龍としての文化――クレオール化と「エートス」
3. 松籟夜話の狙い――聴くことだけが開示してみせる世界の相貌
●第11章 サブライム・フリーケンシーズとAmephoneの冒険――世界の混沌をオールオーバーな耳で捉える
1. 鳥瞰図と聞き覚え――変容し飛躍するイメージの連鎖
2. 崇高なる周波数
3. Amephoneを巡って――モンタージュとコラージュ
4. 混線する周波数
5. オールオーヴァーな聴取の可能性
●第12章 即興的瞬間と音の振る舞い――演奏におけるフィードバック作用について
●第13章 聴取の野性と「遠さ」について
1. 古くて遠い音――聴取の野性を遡る
2. 楽器のDNAを辿る
3. 「現地録音」と発見される「故郷/ルーツ/民謡」
4. 身体に刻印された記憶
5. 幻想ノスタルジアとエキゾティズム、フィールド・レコーディングの危うさ
6. 音楽と「ここではないどこか」
7. 「ここでなければならないどこか」
●第14章 雲のフィールド・レコーディング
1. 雲のフィールド・レコーディング
2. 風のフィールド・レコーディング
3. 雲の〈像〉化
4. 熱学的想像力
5. 精神の気象学
6. パラメトリックな戦略としてのデレク・ベイリーの「反スキル」
7. ウェザーワールドとサウンドスケープ
8. イクィヴァレント――投影を超えて
9. 雲の音
Ⅳ|松籟夜話の周囲/拾遺
●第15章 聴くことの可塑性
1. 聴取の可塑性とは
2. 聴き尽くせない豊饒さ
3. 耳の態勢
4. 音に名前を付けずに聴くこと
5. 星座を描くこと
6. 可塑性の中身
7. 移ろう世界をその都度とらえる
●第16章 即興のフィードバック回路
1. 即興演奏を聴くとはどういうことか?
2. 運動=アクションの様態をとらえる
3. 響きと聴こえ
4. 〈即〉の回路
5. 即興的瞬間
6. 聴くことのダイナミズム
7. 景色と心の間、無意志的想起
8. 徴候と索引、結び目としての身体
9. 飛び火、持続する底流の噴出
●第17章 聴くことを深めるとは
1. 音を楽しむ、音が音楽になる瞬間に立ち会う
2. 聴く=面で触れ合い相互浸透的に感じ取る
3. 聴くことの全身体性、身体に流れ込む音の情動
4. 耳の舞踏(聴くことの即興的瞬間としての)
●第18章 「松籟」考――松籟夜話の「松籟」とは何か
1. 松葉に吹く風
2. 伝統美学からの「切断」
3. 「籟」とは何か・1――三孔の笛
4. 「籟」とは何か・2――「韻」との相違
5. 「籟」とは何か・3――人籟・地籟・天籟
6. 「籟」という原器
7. 灯台としての「松籟」
●おわりに
●「もうひとつの読み方」のための索引
●松籟夜話の灯台群
●人名等索引
著者:
津田貴司(つだ・たかし)
1971年「耳の日」生まれ。音楽家・文筆家。「聴くことと奏でることの汀」で演奏および執筆活動を続けている。
90年代より、ソロ名義hofliや、游音、ラジオゾンデ、スティルライフ、星形の庭など、様々なユニットでフィールド・レコーディングや即興性に基づいた音楽活動を展開してきた。サウンド・インスタレーション制作、ワークショップ「みみをすます」シリーズを継続するほか、福島恵一とともにリスニング・イヴェント「松籟夜話」ナビゲーターを務める。
主なソロCD作品は『湿度計』『水の記憶』『雑木林と流星群』『十二ヶ月のフラジャイル』『木漏れ日の消息』『RECOMPOSTELLA』など。編著書『風の人、木立の人』『フィールド・レコーディングの現場から』(ともにカンパニー社刊)。
福島恵一(ふくしま・けいいち)
1960年東京都文京区生まれ、獅子座、O型。音楽批評。プログレを振り出しにフリー・ジャズ、フリー・ミュージック、現代音楽、トラッド、古楽、民族音楽、フィールド・レコーディングなど辺境を探求。
『アヴァン・ミュージック・ガイド』(作品社、1999年)、『プログレのパースペクティヴ』(ミュージックマガジン、2000年)、『200CDプログレッシヴ・ロック』(立風書房、2001年)、『捧げる――灰野敬二の世界』(河出書房新社、2012年)、『カン大全――永遠の未来派』(Pヴァイン、2020年)、『AA 五十年後のアルバート・アイラー』(カンパニー社、2021年)、『フィールド・レコーディングの現場から』(同前、2022年)等に執筆。2010年3~6月の音盤レクチャー「耳の枠はずし」(5回)に続き、津田貴司とリスニング・イヴェント「松籟夜話」(10回)を開催。
ブログ「耳の枠はずし」(http://miminowakuhazushi.blog.fc2.com/)にライヴ・レヴュー、ディスク・レヴュー等を執筆中。
聴くことを深めるために——2014〜2017年に全10回にわたって開催されたリスニング・イベント「松籟夜話」の記録と考察。
ミシェル・ドネダ、デイヴィッド・トゥープ、フランシスコ・ロペス、ジム・オルーク、tamaru、Amephone、宮里千里、ジル・オーブリー、アルバート・アイラーといった音楽家たちに焦点当てながら、綿密に選定・配列された約200枚の音盤プレイリストをもとに「音をして語らしめる」松籟夜話のドキュメント、そこから浮かび上がるキーワード〈音響・環境・即興〉をめぐる論考・エッセイ・対話から成る全10夜+全18章の592ページ。
〈音響・環境・即興〉の諸相を掘り下げる過程において、著者のリスナー/演奏家としての体験、そして美術、映画、演劇、文学、哲学、建築、都市論、身体論、文化人類学といった他分野の概念・図式を練り合わせて編み出される独自の語法が、来たるべき〈耳〉の態勢を言語化し、「聴くこと」に新たな光を当てる。「音を聴くこと」は単に「情報を読むこと」にとどまらない。音楽の持つ豊かな「汲み尽くせなさ」に、〈耳〉はどのように対峙することができるのか。
▼お取扱店舗
準備中!